1.まえがき
ネットワークの高速化に伴い、音声・映像にCG(Computer Graphics)を加えたフルメディアによる通信アプリケーションの実現・普及がより近い将来のものとなりつつある。
CGにより3次元の仮想現実感を与える空間(仮想空間)を構成し、複数通信者がその空間を共有し各自の身体像(化身:「アバタ」と呼ぶ)を空間内に投影して、空間内移動や空間内における会話を行うシステム(「仮想空間システム」と呼ぶ)は、すでに10年来研究・開発が行われてきている。しかし、個々の空間に閉じた技術開発が主であり、空間横断的に3次元物体やアバタを保持可能なシステムの発表がごく最近なされた以外は、空間相互間の関係や接続に関する研究はほとんど実施されてこなかった。
2.研究概要
インターネットの有力アプリケーションの1つであるWWW(World Wide Web)は、その名が示すとおりネット上に分散した情報をクモの巣状に相互に自由にリンク接続し、相互参照可能としたことが発展の鍵になったと考えられる。しかし、従来の仮想空間システムにおいて、空間相互間のリンク、すなわち参照機能は有効に活用されてこなかった。原因として、仮想空間システムにおいては、他者アバタの存在や挙動など空間内のリアルタイム情報が重要であるのに対し、従来のリンク方式ではリンク先空間へ移動完了しなければ、ユーザにはそれらの情報が得られなかったことが考えられる。その場合、リンク先空間内のリアルタイム情報を捕捉するために、ユーザはリンク先空間への試行入場を繰り返す必要がある。それはユーザにとって高負担であり、リンク先空間の参照行為を阻害するものである。仮想空間システムを次世代のWWWとして発展させようとするとき、空間相互間のリンク使用(参照行為)を阻害するこのユーザ負担をとり除くことが肝要である。そこでその解決策として、リンク先空間内情景の常時提示機能を従来のリンク機能に付加することを提案するとともに、ユーザの空間内視点移動に高速に追随するプログラムとしてその解決策が実現可能であることを検証した。
新リンク方式は見かけ上、リンク先空間をその情景提示面で接続する。ユーザ視点がこの情景提示面をスムーズに通り抜けて空間移動するプログラムが実現可能であることを検証した。この機能付加により、新規リンク方式は実質的に空間接続機能要素となる(ただし、一方向性の空間接続である)。
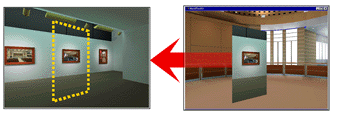
ユーザの欲する任意位置での空間接続 |
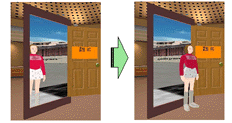
視野を連続的に保ったスムーズな空間移動 |
▲図1 空間接続リンクの外観と特性
新リンク方式をペアかつ双方向で使うことにより、空間を相互連結する空間連結機能要素とするプログラムが実現可能であることを検証した。この機能は、複数ユーザが互いの空間を持ち寄り、あるいは無関係な第三者の空間を参照し、それら複数の空間を相互連結して、ユーザグループで共有する独自の合成空間とする、いわゆる“共同創造空間”を構築可能とするものである。
3.システム構成
システムにおいてユーザ同士は対等なPeer-to-Peerで相互接続する。空間と空間接続リンクの組合せにより構成する“共同創造空間”を共有するユーザグループ内において、共有データの更新はその発生端末から他の端末へ逐次伝達される。また、データ共有グループがメンバ以外の第三者の空間データを参照している場合にも、空間データの更新は第三者のユーザ端末とのPeer-to-Peerネットワーク接続を介して、その空間データを参照するすべてのユーザに対して逐次伝達される。
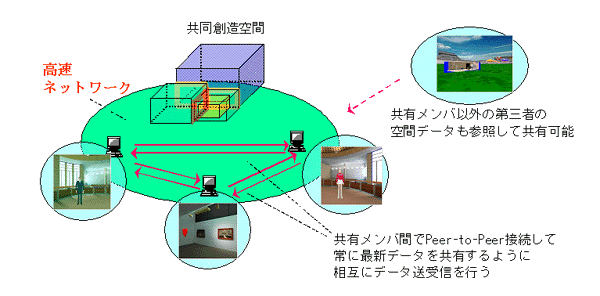
▲図2 高速ネットワークを介して“共同創造空間”の構築とユーザ間共有を実現
4.これまでの成果
次の成果を挙げている。技術内容及びJGNプロジェクトの存在について、国内のみならず国外へも強くアピールしている。
- 国際会議IEEE GlobeCom'2000 ワークショップにおける基本コンセプトの発表
K. Kato and K. Shimamura, ”Reproductive Cyberspace for User Proliferation,”
in IEEE GlobeCom2000(Nov.27, San Francisco)Workshop on "Application
of Virtual Reality Technologies for Future Telecommunication Systems"(Nov.
27,2000)
ユーザを自己増殖的に(増殖:Proliferation)増大させるために、ユーザ自身が仮想空間を自在にカスタマイズ可能とすることが重要であると主張し、空間接続リンクの基本的なコンセプト提案を行った。
- CEATEC JAPAN 2001への出展と新聞報道
日刊工業新聞「3次元ホームページ開発に成功 画面内空間を自由探検」(2001年10月9日)
空間接続リンクをユーザの視点移動に高速に追随するプログラムとして実現した結果を技術展示した。
- 書籍出版による技術内容とJGNプロジェクト紹介
[1]K. Kato and K. Shimamura, “A Hyperspace Link Method for Virtual
Reality Telecommunication Systems,” (Ch. 5) in Virtual Reality Technologies
for Future Telecommunications Systems, John Wiley & Sons Ltd.,
Oct. 2002.
[2]K. Kato, R. Komiya, and K. Shimamura, “High-speed Networks and
Virtual Reality Telecommunication Systems,” (Ch. 15) in Virtual Reality
Technologies for Future Telecommunications Systems, John Wiley &
Sons Ltd., Oct. 2002.
空間接続リンク方式の紹介を行うとともに、まとめでは高速ネットワーク技術との関連を議論し、JGNにおける研究を紹介している。
5.社会的効果
技術分野に対しては、仮想空間相互間の関係や接続に関する研究の重要性、応用可能性を広くアピールするとともに、高速ネットワークを活用する次世代アプリケーション開発の重要性をアピールしている。
現在、すでにインターネット活用の最大級アプリケーションの1つであるWWWに新たな進化の可能性を指し示すものである。
6.まとめ(総括)
3次元の仮想現実感を与える仮想空間システムを次世代のインターネット・アプリケーションへと発展させる可能性を見出すため、空間相互間のリンクとして空間を相互に接続する「空間接続リンク」を新規提案した。このリンク方式はユーザによる仮想空間相互間のリンク作成を活性化し、仮想空間を単位とする次世代のホームページ、いわばホームスペース(Home
Space)としての発展へとつながることが期待される。
今年度末のプロジェクト終了へ向けて、本研究の技術資産を継承するようフリーウェアとして配布することを検討していく。
|